
気になることが頭の中に浮かんできたら、それを無検閲でタスク管理の対象とするのが、一般的なタスク管理の態度でしょう。しかし本当にそれでいいのでしょうか?
タスク管理をシステムにたとえるのであれば、システム運用上、そのシステムに流すデータの品質もまた、管理対象にすることは自然です。いくらシステムが素晴らしくても、誤ったデータが入力されれば、誤った出力がされます。
あるタスクに、「やりたくない」、「先延ばししたい」という属性をつけて入力すれば、システム内でその属性に合わせた処理がなされた上で、それ相応の出力がされた後、実行に移されます。
その処理内容こそが、タスク管理やライフハックのキモであるという人もいるでしょう。
一方、ファストアンドスローでは、システム1やヒューリスティクス、バイアスのせいで、その属性付け自体が誤っている可能性を指摘しています。
ものごと(タスク)に対してどのような気持ちを持つかは、その人の自由。多様性が叫ばれる中、人がどう感じるかの領域は、触れてはならない聖域であり、侵すべからず。なるほど、それが現代社会における正論なのかもしれません。
しかし最高のタスク管理を目指すのであれば、システムもさることながら、システムに流すデータを歪ませるシステム1、ヒューリスティクス、バイアスの影響を最小限に抑える、聖域なき構造改革も、同じかそれ以上に大切ではないでしょうか?
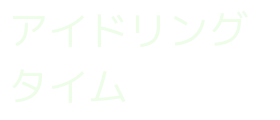


![[#100日チャレンジ]Day 28|瞑想と半断食と低炭水化物の先へ。。](https://idling-time.com/wp-content/uploads/2014/09/100daychallenge_neweyecatch-100x100.jpg)

![[i]アシタノレシピ参加の経緯やアレコレ](https://idling-time.com/wp-content/uploads/2016/10/DSC00172-100x100.jpg)

![[i]文章書くなら覚えておきたいATOKのショートカット10+1](https://idling-time.com/wp-content/uploads/2015/07/20150713-atok-31-100x100.png)
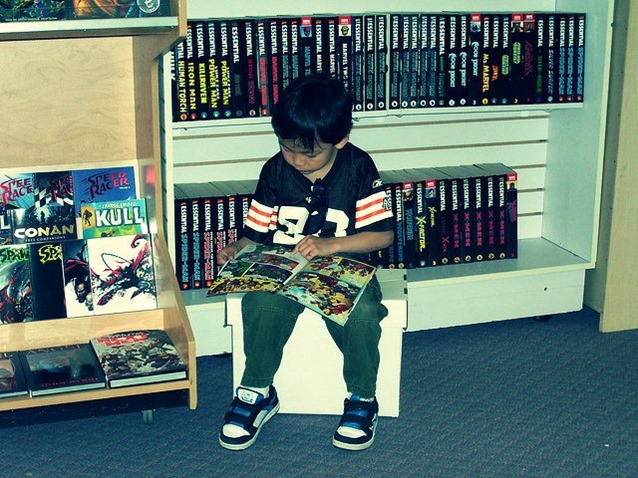
![[i]半デジタルデトックスをやってみたら、真人間になった](https://idling-time.com/wp-content/uploads/2015/08/20150817_digital-detox-100x100.jpg)




